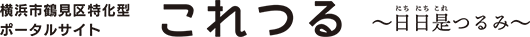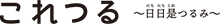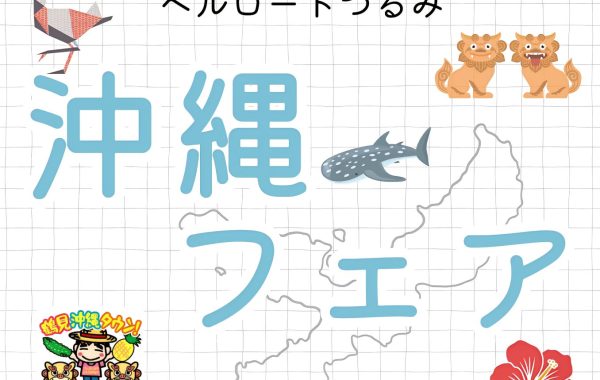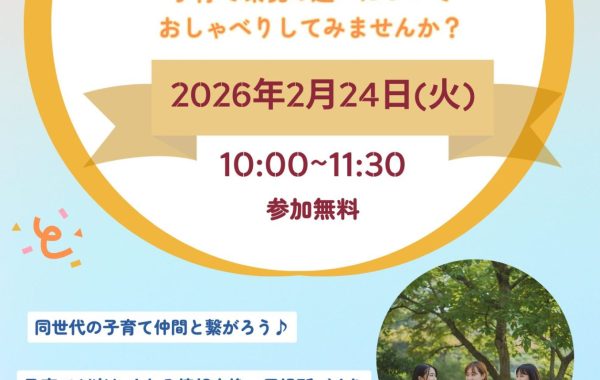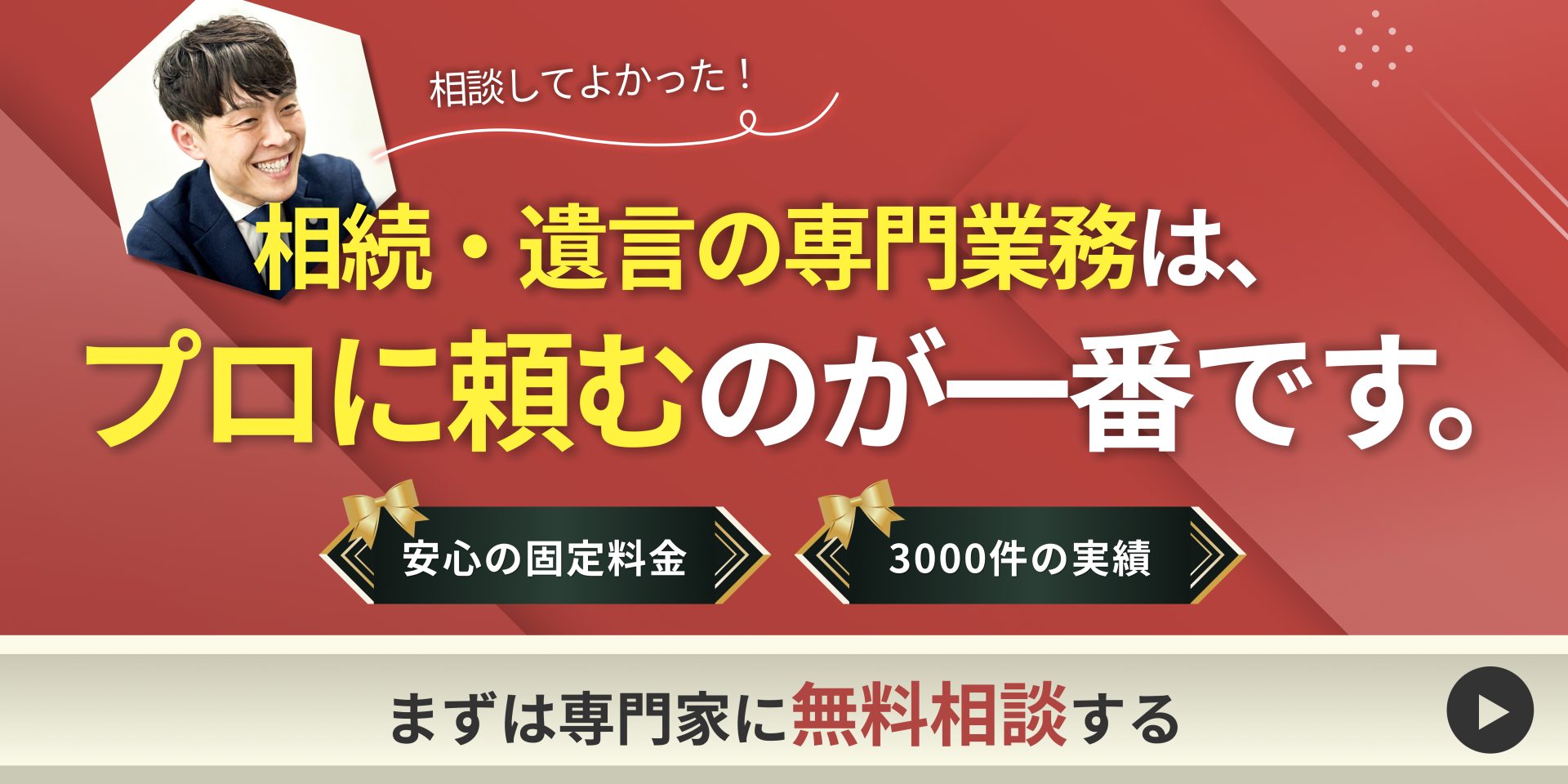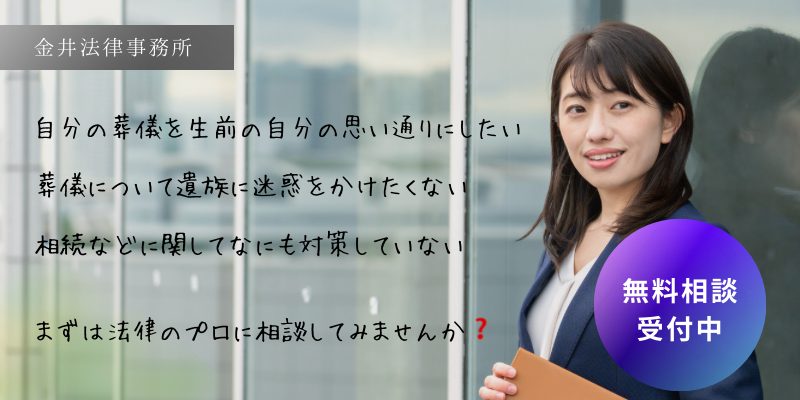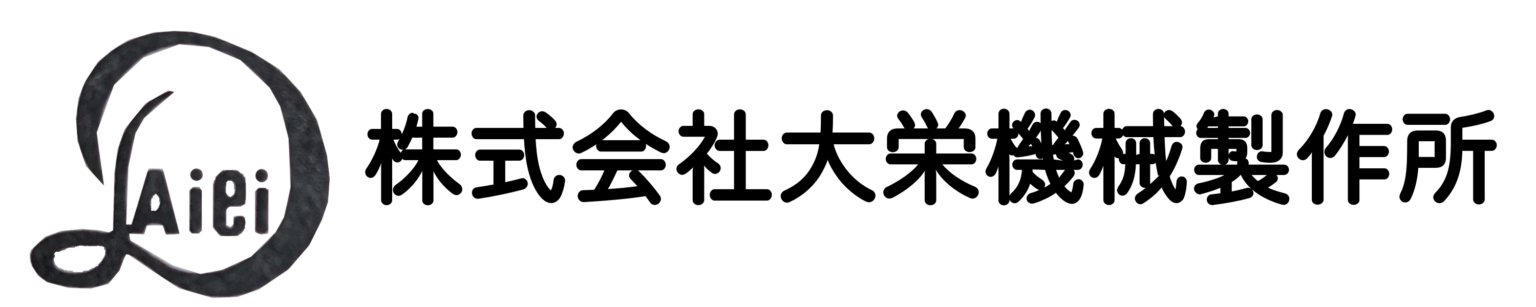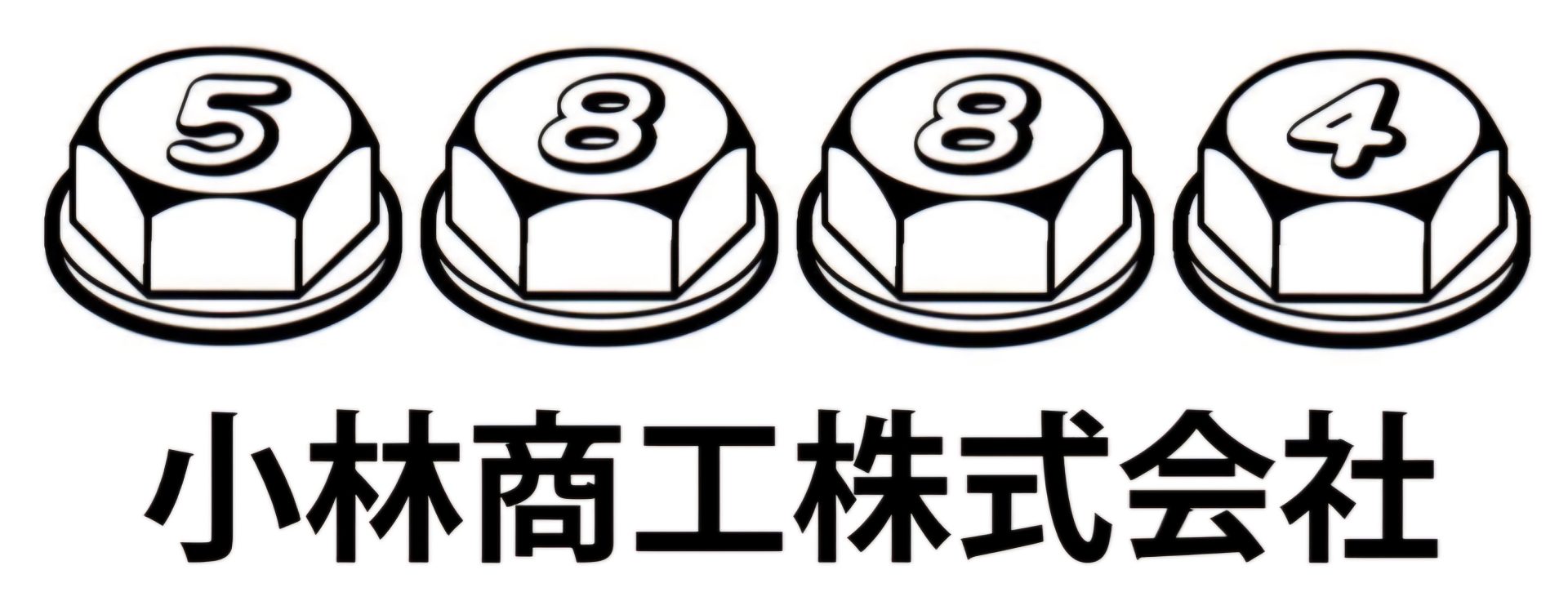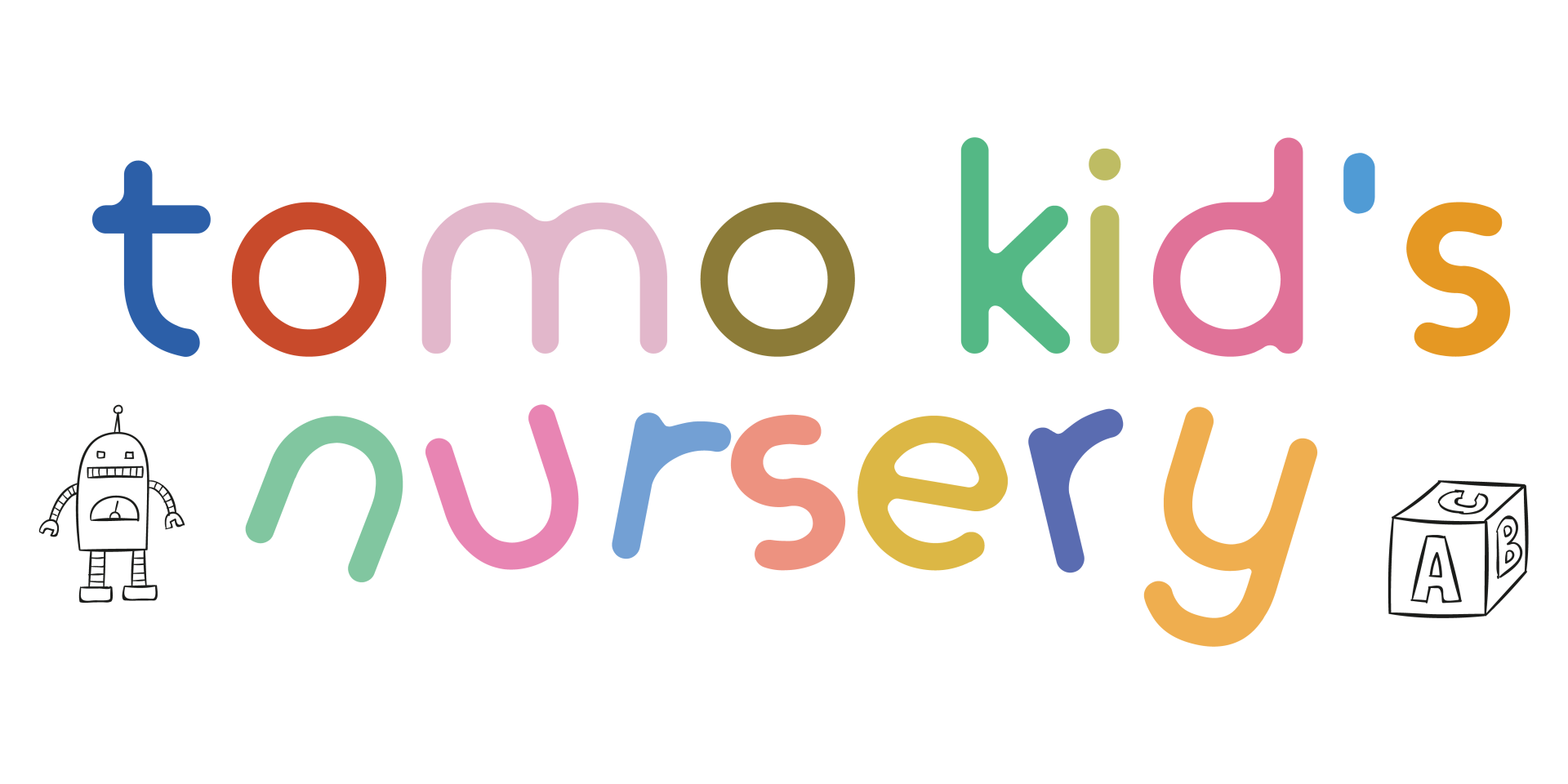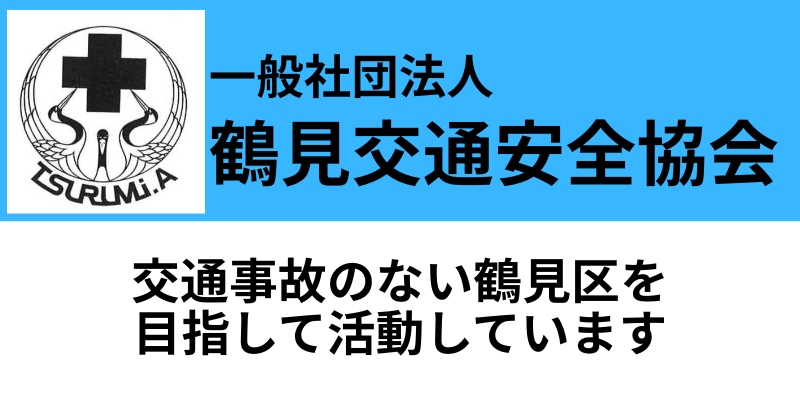鶴見神社「鶴見の田祭り」 今年も〝伝統どおり〟 再興38回目も盛況に

鶴見神社(金子剛士宮司)に鎌倉時代から伝わるとされる民俗芸能「鶴見の田祭り」が、4月29日に行われ、古式ゆかしい稲作の所作で五穀豊穣と子孫繁栄を願った。
田祭りは、神寿歌(かみほぎうた)と呼ばれる節に合わせ、春の鍬入れから秋の収穫までを演じる民俗芸能。その年の豊作と子孫繁栄を願い、地域住民らが伝えてきた伝統行事だ。

春の鍬入れの様子
鶴見神社では、明治5年の鉄道開通にあたり、政府から廃絶命令が出されたことで一度途絶えたが、先代宮司や鶴見歴史の会の尽力で1987年に再興。
現在は周辺町会の地域住民らで成る鶴見田祭り保存会が主催し、今年で38回目を数える。
再興以降、伝統文化ポーラ賞の地域賞、地域伝統芸能大賞・地域振興賞など、全国的な賞を受賞。横浜市地域無形民俗文化財にも指定されている。
近隣学校や区内団体によるステージも
当日は、例年通り境内に特設舞台を設置。周辺には氏子町会などによる模擬店も出され、地域住民らでにぎわいをみせた。
舞台では田祭りの本番を前に、鶴見小学校や豊岡小学校、鶴見中学校といった近隣小中学生によるステージのほか、鶴見邦楽連盟の日舞、横浜雅楽会などが伝統芸能を披露。区内出身のラッパー・Panbitなども出演し会場を盛り上げた。

鶴見中学校吹奏楽部による演奏
「神寿歌」古式ゆかしく
鶴見の田祭りは、明治のころに当時の区長にあたる鶴見戸長や、鶴見神社の宮司も務めた黒川荘三が、幕末から明治時代の鶴見の様子を書き記した「千草」という手記に残された詳細をもとに再興されている。
それにより、今年も夕方から杉山祭と呼ばれる祭典が行われ、演者となる作大将、稲人(いなんど)役などによる道具改めといった儀式を順次進めたあと、18時から神寿歌が開演。
作大将、稲人頭、稲人役の計12人が舞台にあがり、歌に合わせて稲作の所作を演じた。神寿歌の最後には、男女役の「於鶴」(おつる)と「亀蔵」(かめぞう)が登場。子孫繁栄を願い、幕を閉じた。




鶴見小学校のソーラン

豊岡小学校の演技
- 区内出身のラッパー・Panbit
- 鶴見邦楽連盟
- 飲食模擬店もにぎわいをみせた